感染症検査
体内にウイルスや細菌などの病原体が存在しているかどうかを調べる検査です。
感染症検査とは

感染症検査は、体内にウイルスや細菌などの病原体が存在しているかどうかを調べる検査です。症状がはっきりと現れていない段階でも感染の有無を確認することで、早期の診断や適切な治療につなげることができます。また、周囲への感染拡大を防ぐためにも重要な検査です。
当院では、新型コロナウイルス、B型肝炎、C型肝炎、インフルエンザ(迅速検査)、梅毒(血清反応)などの感染症検査を実施しています。発熱や体調不良がある方だけでなく、自費診療として検査を希望される方も受けていただけます。
新型コロナ
ウイルスによる感染症で、発熱・咳などを引き起こします
■抗原検査
抗原検査は、PCR検査よりも短時間かつ簡便に実施できる検査方法で、15〜30分ほどで結果が出ます。感度・特異度はやや劣るものの、医師が患者様の症状や状況に応じて、PCR検査・抗原定性検査・抗原定量検査を適切に使い分けて診療を行っています。迅速な診断と対応が可能ですので、安心してご来院ください。
■PCR検査
PCR検査は新型コロナウイルスの遺伝子(RNA)を検出する高感度な検査で、確定診断に広く用いられています。検体は鼻咽頭または唾液を用い、鼻咽頭検査は綿棒で鼻の奥から採取し、発症10日目以降も高い検出力があります。唾液検査は自己採取が可能で負担が少ない反面、発症9日目までに限り確定診断が可能です。海外渡航証明に用いる際は、鼻咽頭検体での検査が必要です。ご希望の方はスタッフまでお申し出ください。B型肝炎
血液等で感染し、肝臓に炎症を起こす病気です

B型肝炎ウイルス(HBV)による感染の有無を調べる血液検査です。肝炎症状や肝機能障害がみられる場合に、原因がHBVであるかを確認するために行います。
この検査では、HBVの外殻に存在するHBs抗原とその抗体(HBs抗体)、ウイルスの芯にあたるHBc抗原とHBc抗体、さらにウイルスが増殖する際に産生されるHBe抗原およびHBe抗体など複数のマーカーを測定します。
特にHBs抗原が陽性である場合、HBVに現在感染していると判断されます。また、HBs抗体が陽性であれば、過去の感染やワクチンによって免疫がついている可能性があります。
B型肝炎は感染しても症状が出にくいことがありますが、重症化すると劇症肝炎を引き起こすこともあります。劇症肝炎の多くがHBV感染に起因するとされており、早期発見が重要です。
C型肝炎
ウイルス感染で慢性肝炎や肝がんを引き起こします

C型肝炎ウイルス(HCV)への感染の有無を確認する血液検査です。現在感染しているか、過去に感染していたことがあるか、またはキャリア状態かを調べることができます。
検査では、まずHCVに対する抗体(HCV抗体)の有無を確認し、陽性であった場合にはウイルスの遺伝子(HCV-RNA)を検出する検査を行って、現在の感染状態を詳しく評価します。HCVはRNAウイルスであり、HCV-RNAが陽性であればウイルスが体内で活動していると判断されます。
C型肝炎は自覚症状が乏しいことが多く、慢性化しやすい特徴があります。
他の肝炎と比較して肝がんに進行するリスクが高く、B型肝炎と比べて約5倍の発がん率が報告されています。そのため、早期の発見と治療が重要です。
インフルエンザ
発熱や咳を伴うウイルス性の急性呼吸器感染症です

インフルエンザウイルスへの感染が疑われる場合に、感染の有無を短時間で確認するための検査です。発熱やのどの痛み、倦怠感など、インフルエンザの典型的な症状が現れた際に行います。
検査は、喉や鼻の粘膜を綿棒でぬぐって検体を採取し、専用の検査キットで行います。約15分程度で結果が判明し、迅速に診断・治療につなげることができます。
インフルエンザウイルスにはA型・B型・C型の3種類がありますが、一般的な迅速検査キットでは主にA型とB型の判別が可能です。毎年冬に流行するのはこのA型・B型であることが多く、迅速検査は臨床現場で広く用いられています。
インフルエンザは毎年冬に流行する感染病です。気になる症状がある場合、蔓延や重症化を防ぐためにも早めにご相談ください。
マイコプラズマ
子どもや若年層に多い咳が長引く肺炎の一種です

マイコプラズマ感染症は、Mycoplasma pneumoniaeという細菌によって引き起こされる呼吸器感染症で、特に子どもから若年層に多くみられます。主な症状は、発熱、乾いた咳、喉の痛みなどで、一般的な風邪に似ていますが、咳が長引く傾向があります。肺炎を起こすこともあり、「非定型肺炎」の一種として知られています。感染は主に飛沫によって広がり、学校や家庭などで集団感染することもあります。重症化はまれですが、注意が必要です。
梅毒検査
トレポネーマという細菌が引き起こす性感染症です
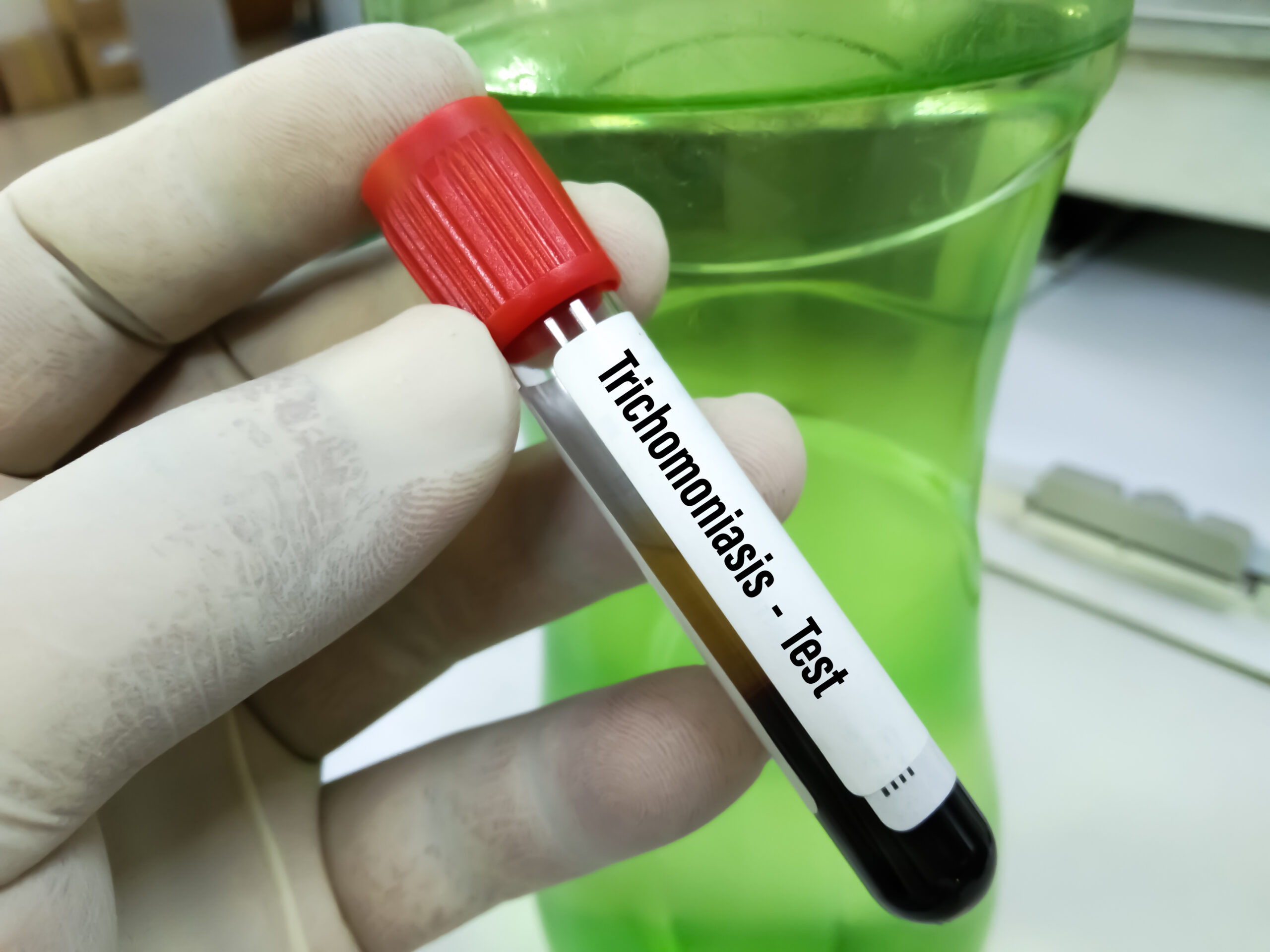
梅毒は、Treponema pallidum(TP)という細菌に感染することで発症する性感染症です。初期には痛みのないしこりや発疹が現れることがありますが、無症状のまま進行することも多く気付かないうちに体内で病気が進んでしまうことがあります。
検査には、TP抗原を使って病原体そのものに対する抗体を検出する「TP法」と、脂質抗原を用いて体内の免疫反応を調べる「STS法(非トレポネーマ試験)」の2種類があります。これらを組み合わせることで、感染の有無や病気の進行状態をより正確に把握することができます。

